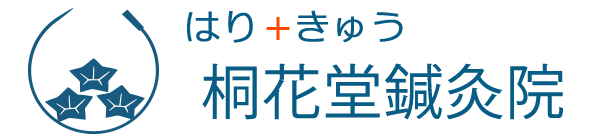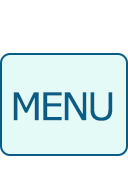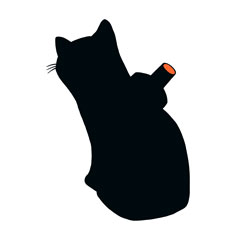胃の不調は万病の元、夏バテの原因にも
東洋医学の知恵 宮下東洋医学の中にも色々な流派があるのですが、その中に補土派という一派があります。「補土」はそのまま読めば「土を補う」ということですが、ここで言う「土」は「胃」という意味です。つまり、補土派は胃を大切にする流派ということになります※1。

胃をいたわる
補土派の開祖と呼ぶにふさわしい人物といえば、李東垣です。東垣は晩年の1249年に『脾胃論』という著作を完成させ、現在も広く読み継がれています。その中では、補土派の基本思想について以下のように説明しています。
元気の充足は、皆脾胃の氣傷れる所なきに由りて、而る後に能く元氣を滋養する。『脾胃論』脾胃虚實傳變論
(元気之充足、皆由脾胃之氣無所傷、而後能滋養元氣。)
つまり、胃がしっかりとしていれば、元気が充足するので、結果として病の治癒を早めたり、健康を維持することもできるということです。
今回は、この『脾胃論』という文献から、胃をいたわることの重要性について考えてみました。
胃が悪いと夏バテしやすくなる
胃の調子が良いことが全身の健康につながるというのが『脾胃論』の思想なわけですが、逆に、胃が虚弱であると、様々な全身的な不調をきたします。『脾胃論』の中には、「胃の氣が虚すと、耳目口鼻がともにこのために病んでしまう※2。」とあり、通常胃とは関係のなさそうな器官の病気とも関連づけられています。
また、胃がしっかりしていないと、気候の変動に対する適応力が低下するようで、特に湿気や熱気の強い時期に体調を崩しやすくなり、持病を悪化させることもあるようです。日本の場合は、梅雨から夏に調子が悪く、夏バテしやすい方は、普段から胃をいたわる生活を心がけるようにすればよいかもしれません。
胃をいたわる3箇条
『脾胃論』には胃を悪くする原因についても色々と触れられていますが、胃をいたわるにはそれらを避ければよいので、実践しやすそうなものを以下の3箇条としてまとめてみました。
- 其の一 過飲食を避ける
- 其の二 刺激の少ない物を食べる
- 其の三 ストレスを避ける
大変地味であたりまえな3箇条になってしまいましたが、以下に東洋医学的な解説を加えます。
過飲食はなんと不眠の原因にも
食べ過ぎや飲み過ぎを避けるのは、胃をいたわる最も効果的な方法です。ただ、お酒を控えたり、食欲をコントロールするのは意思の力に頼るため、なかなか実行が難しいところですね。
また、過食は不眠の原因とも考えられています。『脾胃論』では、満腹で眠れない時の解決策が記載されていますが※3、その場合は、布団の中で眠くなるまで粘るより、起きて軽く活動することで解決できるようです。
刺激の少ない物を食べる
お酒や、過度に冷たい物や熱い物がまず基本として避けるべき刺激物です。また、本草学的に「辛熱」の性質を持った物も摂り過ぎないようにしましょう。
この「辛熱」とは、味が辛くて身体を温める食材のことで、唐辛子などのスパイスがこれにあたり、日本人はあまり使わない八角も避けるべき物として考えられています。また、お好きな方も多いと思いますが、ショウガパウダーなどの「乾姜」もほどほどにした方が良さそうです。
胃を調えることでストレスの影響を軽減
精神的ストレスは主に「心」へ悪影響を及ぼし、それが様々な症状を起こす引き金となります。東洋医学では「心」と「胃」はちょうど「母」と「子」の関係のように考えられています。ストレスによって「胃」の母である「心」が不調になると、その子である「胃」も影響を受けて病んでしまうわけです。
そのため、ストレスによって体調を崩している場合は、「心」に対する治療だけでなく、同時に「胃」を調えるとよいと考えられています※4。
根本的なストレスを解決するのが最も望ましいですが、仕事や家庭が関わる場合は、現実としてストレスを避けることが不可能です。せめてストレスが身体に与える影響を少しでも軽くするために、普段から胃をいたわっておきましょう。
腹八分目に病なし
『脾胃論』には「胃が弱ることで百病を生ずる※5」とあるように、胃の不調は全身に影響を与えます。少々大げさな所もあるかもしれませんが、日頃から少なくとも飲みすぎや食べ過ぎに注意したり、スパイス中毒の方は量を抑えるようにして、胃に優しい生活を送るようにしたいですね。
「腹八分目に病なし」という諺は、東洋医学的には大変すぐれた養生の方法なわけです。
- ※1:「脾胃」いう言葉が通常使われますが、ここでは一般の方にわかりやすいように「胃」で統一しています。
- ※2:「胃氣一虚、耳目口鼻、倶爲之病」『脾胃論』脾胃虚實傳變論
- ※3:「飽而睡不安、則少行坐」『脾胃論』摄養
- ※4:『脾胃論』では、心火が脾に乗ずると表現されており、また、七情の乱れによる病を治療する方法として、「善治斯疾者、惟在調和脾胃、使心無凝滞」(安養心神調治脾胃論)とあります。
- ※5:「胃虚則五臓、六腑、十二経、十五絡、四肢、皆不得営運之氣、而百病生焉」大腸小腸五臓皆属於胃胃虚則倶病論